
出会いの衝撃
―そもそも小西修さんと知り合ったきっかけから教えて下さい。
村上 前作「東京干潟」(注1)で多摩川の河原で猫と暮らすおじいさんを撮った縁で、小西さんと知り合いました。実はお会いする以前から、小西さんのことは存じ上げていました。この映画でも話が出てきますが、NHKで小西さんご夫妻を取材したドキュメンタリー番組(注2)があって、それを見て「世の中にはすごいことをしている人がいるなあ」と感心し、小西さんご夫妻のことが強く印象に残りました。その後、小西さんが開催した写真展で「東京干潟」のおじいさんの飼い猫の写真が展示されるというので、見に行った際に初めてご本人とお会いしました。
―その時の印象はいかがでしたか。
村上 小西さんご自身はテレビで受けた印象のまま、一見とても淡々としている方でしたが、その奥に猫やホームレス人たちへ向けている優しいまなざしを感じました。また何よりその時は、小西さんが撮った写真とその下に掲示されているキャプションに衝撃を受けました。写っている猫たちのその後が記されていたのですが、ほとんどの猫が死んでいて、しかも大半が虐待によるものでした。こんなことが多摩川で人知れず行われているのかと、とてもショックでした。
―そこで興味を持って、小西さんを取材したいと思ったわけですね。
村上 いえ、その時は「東京干潟」を撮影中でしたから、そのような考えは浮かんでこなかったです。ただもう多摩川の猫たちの過酷さと人間の残虐性の一端を知らされて、現実の重さに打ちのめされた感じでした。
2-1024x576.jpg)
7-1024x576.jpg)
撮れるとは思わなかった
―そこからどうして小西さんを撮ることになったのでしょうか。
村上 「東京干潟」が完成し、一緒に製作した「蟹の惑星」(注3)と共に上映活動を行っている時に、小西さんを知る何人もの方々に「次は小西さんを撮るんでしょう?」と言われました。「東京干潟」で取材したおじいさんからも強く薦められました。でも私は小西さんの長年に及ぶ活動の大きさを知っていましたから、例えば数年取材しても、小西さんの活動の一端しか捉えられないし、それほど大きなものの軌跡を描き切る自信はありませんでした。また、小西さんは自転車や徒歩で多摩川を巡り、日々長距離を移動するので、体力的にも続けられるのだろうかという不安もありました。
―それでも撮ろうという心境に変わったのはなぜですか。
村上 2020年3月に小西さんが多摩川の橋げたを利用して、多摩猫たちの写真展を開いたんです。小西さんの知り合いのミュージシャンの方々がライブを行ったり、近くに暮らしているホームレスの人たちも集まって、和やかな雰囲気の催しでした。私も伺ったのですが、そこで見た猫たちの写真に改めて衝撃を受けたんです。というのは、会場がまさに猫たちが棄てられ、そして死んでいった多摩川なわけで、その空気や匂いの中で写真を見ていくと、猫たちの存在がにわかに肌身で感じられました。彼らは確かに存在し、そして残念ながら消えていった。その命の儚さがずしんと胸に響きました。その時、初めて多摩川の猫のことを小西さんの活動を通して記録したいと思いました。
―その体験がきっかけで小西さんへ取材を申し込んだと。
村上 お忙しい中、小西さんに時間を作っていただき、ご自宅近くの居酒屋で取材のお願いをしました。小西さんはテレビの他にも新聞や雑誌など、様々なメディアの取材を受けているし、また私の前作も見て下さっていたので、快く承諾をして下さいました。どういう意図でどういう作品を作るつもりなのかとか一応説明はしましたが、それ以上深く聞かれることはありませんでした。そして撮影では自転車が必要になるので、小西さんの最寄り駅近くの駐輪場に自転車を常置しておくことが前提ということで、近くのサイクリングショップを紹介していただき自転車を購入しました。
3-1024x576.jpg)
2-1024x576.jpg)
密着取材が不可欠
―実際に撮影を始めてどんなことを感じましたか。
村上 この映画の撮影は、2020年4月2日、新型コロナウイルスに対して政府が初めて緊急事態宣言を発令する1週間前から始まりました。いわばコロナ禍と共にスタートしたんです。でも多摩川の猫たちにとって緊急事態宣言など関係ないし、小西さん曰く「多摩川はいつも緊急事態」というわけで、それまでと変わらず日々出かけていくということでした。私もコロナの影響で上映や仕事が減ってしまい、そのおかげと言ってはなんですが、毎日のように小西さんに密着して撮影を続けました。撮影期間は2年ほどですが、これだけ頻繁に出動した撮影は初めてでした。
―全編にわたって小西さんの活動の様子が綿密に綴られていますね。
村上 結果的にこの作品は、小西さんにどれほど密着できるかということがカギだったと思います。小西さんの活動範囲は、多摩川の猫が棄てられている全域になります。人が住んでいるところには、残念ながら棄てられる猫が存在します。ですから上流の奥多摩から下流の河口部までが活動範囲となります。その日によって行く場所を決めて、自転車で行ける場所は自転車で隈なく周り、遠いところは電車で赴き、あとは歩いて河原を巡ります。一日何十キロも移動することもあります。川には右岸と左岸の両岸がありますから、膨大な活動範囲になります。その中で、映画にあるように各地のホームレスやボランティアの人たちを訪ねて、猫の様子を見守っていくわけです。ですから全ての場所を一通り回るだけでも数か月かかりました。こちらの都合でとびとびに撮影に行っていたのでは、とうてい全部を把握できなかったし、一度行っただけでは撮影できることは限られていますから、何度も各所に通うためには密着取材が不可欠でした。
-1024x576.jpg)
1-1024x576.jpg)
小西さんへの厚い信頼
―撮影の中でどんなことが見えてきましたか。
村上 多摩川の猫も人も小西さんをとても信頼しているということです。例えば僕が一人でカメラを持って取材させて下さいと、いきなり頼み込んでもホームレスの人もボランティアの人も許可はしてくれないでしょう。でも「小西さんの取材ならいいよ」と、初対面の人でも撮影を許してくれる。いかに小西さんが信頼されているかを感じました。これは長年に渡って築いたもので、そう簡単には生まれない厚い関係だと思います。ホームレスやボランティアの人たちは、それぞれに連携はなく、いわば個別で猫のために奮闘しているのですが、小西さんが支援したり、困ったことがあれば相談にも乗ってくれることで、大きな安心感を持つことができます。小西さんを通じて多摩川の見えない連帯感のようなものを、皆さんが感じているのがわかりました。
―小西さんと多摩川の人々の信頼関係は映画に滲み出ていますね。
村上 取材を始めてそのことがだんだん分かってきて、この映画が何を描くべきなのかが見えてきました。映画を撮る前は小西さんの膨大な活動の軌跡を描くのはとても無理だと感じていましたが、そこを描くのではなく、小西さんが日々見ている世界、猫と人を通じての多摩川の日常、その交流のなかで起こることを記録していこうと思いました。
―映画には様々な猫が登場しますが、彼らの風貌がまた印象的です。
村上 初めて多摩川の河川敷で暮らす猫たちの姿を間近で見た時は驚きました。厳しい環境に耐えてきた労苦が表情に現れているんです。見つめ返されると、ドキッとするような、人間を恨んでいるかのような、それだけ多くの厳しさに耐えてきたということだと思います。小西さんや多摩川の人々は、そんな猫たちに、もう一度人間への信頼を取り戻してもらえるようにと日々活動を続けているのだと思います。
-1-1024x576.jpg)
1-1-1024x576.jpg)
妻・美智子さんの活動
―小西さんから撮影に関しての要望などはあったのでしょうか。
村上 特にはありませんでした。ただ、ホームレスの人たちのなかには、撮られたくない人も当然いらっしゃるので、その点は小西さんにも配慮するようには言われましたし、私も気を付けました。あとは撮影の早い段階で、小西さんから奥さんの活動についても撮ってほしいと告げられました。それは小西さんの奥さんへの敬意の現れだと思います。奥さんの美智子さんは、基本的に小西さんとは別に猫の救護活動をなさっていますが、こちらもとても大変なことを続けていらっしゃるので、小西さんの美智子さんのへ思いを受け止めつつ、ぜひとも撮らせていただきたいと思いました。
―奥さんは野外の猫と、そして自宅でも猫を世話されていますね。
村上 そもそもお住い近くの緑地公園に棄てられた猫たちの世話を美智子さんが始めたのが、それぞれの活動のきっかけでした。美智子さんは約30年に渡って、雨の日も雪の日も体調がすぐれなくても、毎日必ず決まった場所をまわり、猫たちの世話を続けています。さらに自宅に病気やケガを負った猫を何匹も引き取り、昼夜を問わずケアしています。その行動力と信念には本当に圧倒されます。小西さんも美智子さんをとても尊敬しているように思いました。小西さんは内面に優しさ秘めていますが、普段はあまり自分の心情などは話さないタイプです。反対に美智子さんは、内面に溢れる慈悲深さが言葉となって湧き出てくるタイプで、猫への愛情を全身で表現されます。このご夫婦の対照的な個性がとても興味深く、それぞれのお話を個別に聞くことで、お二人の互いの活動への思いを知ることができました。

6-5-1024x576.jpg)
人間のなかにある希望を信じたい
―映画の中では猫への残酷な虐待事件も起こりますね。
村上 この映画を作るにあたって、猫への虐待については避けて通れません。取材した2年間のなかで、虐待事件は各地で繰り返し起こりました。ただ実際に虐待の現場そのものに遭遇することはありませんでした。そもそも虐待は他人が見ていない時を狙って行われるので、めったに遭遇できません。世話をしているホームレスやボランティアの人たちが犯行直後に逃げていく人を見たり、また遠目で目撃したりとか、あとは虐待の現場に残された棒きれや凶器などで虐待が行われたこと知るわけです。猫にエサを与えるために置いてある食器や寝床が破壊されていて、虐待が行われたのを知ることもあります。
―なぜ虐待は繰り返されるのでしょうか。
村上 私もそれを常に考えながら撮影を続けていましたが、一概には言えないと思います。小西さんにお聞きしても、それははっきりとはわからないとおっしゃいます。何らかの理由で猫が嫌いだという人もいるかもしれませんし、野外で猫を世話することを不快に思う人もいるかもしれません。また、ストレスや不満の矛先を弱い猫に向ける人もいるかもしれません。虐待する人の内面は想像では語ることは出来ないと思います。もしかしたら本人ですら、はっきりとした動機がわからないまま虐待をしている可能性もあります。ただ私がこの撮影を通して感じたのは、人間の心の中にはそのような残虐性があり、何かのきっかけでそれが発動してしまう危険性がある、それは誰の心の中にも潜んでいる、しかし一方で、虐げられた命を守りたいという思いも、人間の中には確かに存在しているということです。小西さんご夫妻をはじめ、多摩川で猫を世話している人たちと接していると、そのことを実感します。私はそこに人間の中にある希望を感じました。
―人間の中には残虐性もあるが、一方で命への慈しみもあると。
村上 この映画は多摩川の猫について描いていますが、虐げられ消えていく生き物の命は、他にもたくさんあると思いますし、もっと言えば人間の世界においてでもそうですよね。軽く扱われ、無残に消されていく命のなんと多いことか。でも多摩川の猫と人々の関係を見ていると、私は絶望を感じません。なぜなら小さな命を懸命に守ってくれていている人たちがいるからです。小西さんはもちろんですが、多摩川のホームレスの人たちは厳しい生活の中から、必死に猫のエサ代を捻出して自分は食べなくても猫は飢えさせないようにしています。ボランティアの人たちも、毎日河原に足を運んで、人によっては一日に何度もエサを与えにくる人がいます。美智子さんのように、天候や体調に関係なく、何があっても必ず世話をしにやってくる人がいます。皆さん、なぜそこまでやるのか。きっと命の重さを感じていらっしゃるのではないでしょうか。私はそこに人間への信頼を感じました。人間には命を大切にしたい、それが自分以外のものでも大事にしたいという思いが、本能のように存在するのだと信じます。
―最後に何か付け加えることはありますか。
村上 多摩川になぜ猫がいるのか。それは人間が棄てたからです。猫や犬などのペットは野生動物ではありません。長い時間をかけて人間と共に生きることを余儀なくされた、いわば人間に依存しないと生きていけない動物です。ですからペットを飼うなら、飼い主が責任をもって最後まで面倒をみなくてはならないと思います。ペットはなぐさみものやおもちゃではく、生きている命ですから。多摩川の人たちも、本当は過酷な河原の環境で暮らす猫がいなくなって欲しいと思っているはずです。猫は人と共に暮らしていくのが本当の姿なのですから。


(注1)村上浩康監督の2019年の作品。多摩川の干潟でシジミを獲りながら猫たちと暮らす老人を描いたドキュメンタリー。新藤兼人賞金賞、門真国際映画祭最優秀ドキュメンタリー作品賞など高く評価された。
(注2)ETV特集「ひとりと一匹たち 多摩川 河川敷の物語」小西夫妻の活動とホームレスの男性と猫の暮らしを取材したNHKの2009年放送の番組。
(注3)多摩川河口の干潟で独自にカニの研究を続けている吉田唯義さんと共に、カニの生態を見つめたドキュメンタリ―。「東京干潟」と同じ場所が舞台であることから、村上監督は2本を同時に製作した。
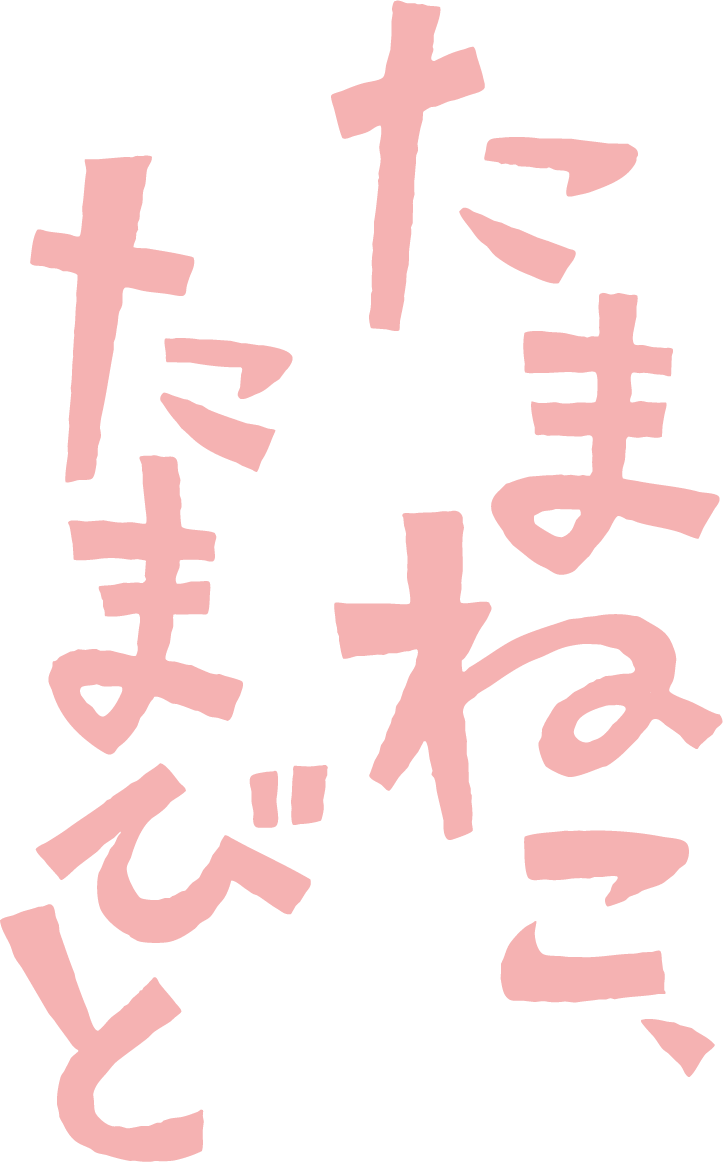
©EIGA no MURA
お問い合わせ

